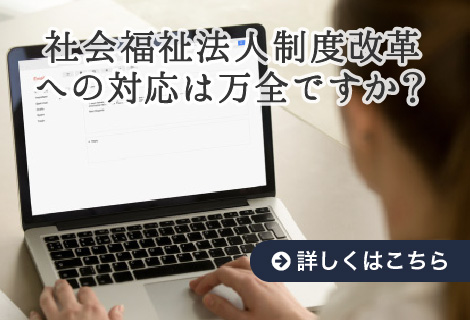社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応について番外編2
社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応について番外編2
社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応について番外編2
前回、固定資産でない財産の管理の必要性と、現物管理の対象とするのかの範囲やその管理手続きを決める必要性について述べました。今回は、その実務としてどのような手続きをすべきかについて、これまでの法定監査や指導監査等の経験から、具体的にヒントになる事項を述べたいと思います。
まず、決めなければならないのは、法人の経理規程やそれに基づく物品管理規程などの規則を規定することが必要です。何故、物品を管理するのか、その範囲は何か、物品を管理する手続きを行う根拠として、経理規程や物品管理規程にそうしたことを規定します。
これで、法人として組織的に物品を管理するルールを定めることになりますので、これらの規程や規則に基づき実施することが明確になります。
次に、決めなければならないのは、現物管理する対象です。前回の例で言えば、パソコンやカメラなどの電子機器は比較的高額なものであり、簡単に場所の移動ができますので、なくなりやすいものと言えます。
一方、文房具やコピー用紙などの消耗品はどうでしょうか。比較的安価で簡単に場所の移動ができるのは電子機器と同じですが、仮になくなってもすぐ代用できるものがあることから、こうした消耗品は対象から除外した方が良いかもしれません。
この辺は、前回も述べたように、社会福祉法人の事業内容、法人規模、拠点数、金額的重要性などを勘案して法人自ら決めるしかありません。一律的な基準を設定することは実態を反映しないからです。したがって、現物管理の対象とする物品と対象外の消耗品を法人の実態に照らしてその範囲を決める必要があります。これができれば、自ずと現物管理する対象範囲が決まりますので、それを規定や規則で規定する流れになります。
最後に、決めなければならないのは、現物管理する手続きです。すでに固定資産の管理規程はあるでしょうから、それに準じて現物管理を行う手続きを規定することになります。ここで留意すべきは、固定資産との違いです。平たく言えば、どこまで固定資産の管理に準じて行うかどうかの判断になります。あまり厳格に規定すると、後の手続きが大変になります。この辺も法人の方針を決めてどこまで簡便的に行うかを規定することになります。
- 2021.08.04お知らせ
社会福祉法人における内部取引の消去について - 2021.03.08お知らせ
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の会計処理について - 2020.07.10お知らせ
「小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関する事務処理体制支援等に関する調査研究事業報告書」について - 2020.06.01お知らせ
社会福祉法人の指導監査の現場から3 -会計伝票の入力と承認手続きについて-
- 2024.03.01お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会 報告書の公表について(その2) - 2024.02.16お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会 報告書の公表について(その1) - 2023.12.20お知らせ 公益法人
公益認定法施行規則改正に関するパブリックコメント結果について - 2023.09.05お知らせ 公益法人
令和5年度公益法人の会計に関する研究会の開催について - 2023.08.07お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会(令和5年度)の開催について - 2023.06.21お知らせ 公益法人
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告の公表について - 2023.05.01お知らせ 公益法人
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告(案)の公表について - 2023.03.16お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その4)-私学法改正案の閣議決定・国会提出- - 2023.03.06お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その3)-監事、会計監査人- - 2023.02.20お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その2)-理事、評議員- - 2023.02.13お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その1) - 2023.01.26お知らせ 公益法人
特定費用準備資金が財務三基準に及ぼす影響について - 2023.01.05お知らせ 公益法人
公益法人の立入検査前のチェック項目について(その2) - 2022.10.20お知らせ 公益法人
公益法人の立入検査前のチェック項目について(その1) - 2022.09.15お知らせ 行政・自治体
総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」の開催について - 2022.08.24お知らせ 公益法人
大阪府所管公益法人における別表Hの対応について - 2022.07.15お知らせ 公益法人
内閣府「特費のすすめ」の公表について - 2022.06.29お知らせ 行政・自治体
地方公共団体におけるインボイス制度への対応について - 2022.06.08お知らせ 公益法人
「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」の追加等について - 2022.05.25お知らせ 非営利法人全般
非営利組織のモデル会計基準における純資産の区分について - 2022.05.10お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その4 - 2022.04.15お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その3 - 2022.04.07お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その2 - 2022.03.25お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その1 - 2022.03.08お知らせ 公益法人
公益法人の定期提出書類等の様式変更について - 2022.02.09お知らせ 公益法人
内閣府「令和3年度公益法人の会計に関する研究会」(第51回・第52回)の議事公表について - 2022.01.19お知らせ 公益法人
「今なら間に合う!剰余金の解消策~特定費用準備資金~」(大阪府法務課)について - 2022.01.07お知らせ 公益法人
公益法人等に対する消費税課税について② - 2021.12.09お知らせ 公益法人
公益法人等に対する消費税課税について① - 2021.10.19お知らせ 公益法人
公益法人等に対する法人税課税について - 2021.09.13お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体包括外部監査に関する監査手続事例~公営企業編~」の公表について - 2021.09.02お知らせ 公益法人
公益法人定期提出書類「別表H」の改訂について - 2021.07.06お知らせ 公益法人
「決議の省略」における議事録・同意書の備置きについて - 2021.06.21お知らせ 行政・自治体
地方公営企業における消費税の決算上の取扱いについて - 2021.05.31お知らせ 公益法人
公益法人FAQの追加・修正について - 2021.05.10お知らせ 公益法人
「令和2年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」の公表について - 2021.04.16お知らせ 行政・自治体
監査専門委員の活用について - 2021.04.01お知らせ 公益法人
公益法人における「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」について - 2021.02.24お知らせ 公益法人
公益法人等の消費税申告における持続化給付金の取扱いについて - 2021.02.05お知らせ 公益法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正について - 2021.01.12お知らせ 学校法人
高等学校等就学支援金制度及び高等教育の修学支援新制度の会計処理について - 2020.12.28お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染拡大に係る家賃支援給付金の公益法人等への適用について - 2020.12.09お知らせ 公益法人
「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ案)」について - 2020.11.24お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その4)】監査委員と内部統制 - 2020.11.12お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その3)】 自治体における内部統制の特徴 ② 自治体における「内部統制の構成要素」の特徴 - 2020.10.30お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その3)】 自治体における内部統制の特徴 ① 「業務の効率的かつ効果的な執行」を重視 - 2020.10.14お知らせ 公益法人
公益法人等における持続化給付金の申請について - 2020.10.01お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2)】内部統制とは ③COSOの内部統制フレームワーク - 2020.09.23お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2)】内部統制とは ②日本にやって来た内部統制 - 2020.09.09お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2】内部統制とは ①アメリカ起源の内部統制 - 2020.08.26お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その1)】地方自治法の改正と内部統制について - 2020.08.13お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(序)】自治体内部統制シリーズ連載開始にあたって - 2020.08.03お知らせ 行政・自治体
統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査について - 2020.07.20お知らせ 公益法人
大阪府における公益法人立入検査の実施について - 2020.06.29お知らせ 公益法人
「令和元年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」及び「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正」の公表について - 2020.06.11お知らせ 行政・自治体
「地方公会計の推進に関する研究会(令和元年度)報告書」の公表について - 2020.04.27お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(4) - 2020.04.14お知らせ 公益法人
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.14お知らせ 学校法人
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.14お知らせ 非営利法人全般
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.10お知らせ 学校法人
非営利組織の監査報告書の改正について(3) - 2020.04.10お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(3) - 2020.03.30お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(2) - 2020.03.13お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催についてその3 - 2020.03.12お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催についてその2 - 2020.03.02お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について - 2020.02.28お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会近畿会公開シンポジウム 「地方自治体の新たな時代の幕開け~内部統制制度制度導入への取組み~」参加報告 - 2020.01.20お知らせ 公益法人
第1回公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 - 2020.01.04お知らせ 公益法人
公益法人及び学校法人のガバナンス改革について - 2020.01.04お知らせ 学校法人
公益法人及び学校法人のガバナンス改革について - 2019.12.23お知らせ 非営利法人全般
日本公認会計士協会「非営利組織における財務報告の検討」について - 2019.12.03お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の「監査報告書」の改正について - 2019.10.23お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準の改訂について(リマインド) - 2019.10.07お知らせ 学校法人
私立学校法の改正について② - 2019.09.25お知らせ 学校法人
私立学校法の改正について① - 2019.09.13お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公会計の論点と方向性」の公表について - 2019.08.30お知らせ 行政・自治体
総務省「地方公会計の推進に関する研究会(令和元年度)」の開催について - 2019.08.20お知らせ 公益法人
公益法人に対する勧告案件について - 2019.08.09お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について③ - 2019.07.31お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について② - 2019.07.16お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について① - 2019.07.05お知らせ 行政・自治体
水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について - 2019.06.20お知らせ 行政・自治体
内部統制ガイドライン及び監査基準(案)の公表について - 2019.06.11お知らせ 公益法人
(公益法人)電子申請システムにおけるエラーコードについて - 2019.05.30お知らせ 公益法人
「公益法人information」新たな電子申請システムの稼働について - 2019.04.19お知らせ 公益法人
「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」について - 2019.04.08お知らせ 公益法人
「平成30年度公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」の公表 - 2019.03.30お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について④ - 2019.03.22お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について③ - 2019.03.08お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について② - 2019.02.18お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について① - 2019.02.06お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて⑤ - 2019.01.07お知らせ 行政・自治体
総務省「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」の開催について - 2018.12.28お知らせ 独立行政法人等
国立大学法人会計基準の改訂について - 2018.12.22お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて④ - 2018.12.10お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて③ - 2018.11.29お知らせ 学校法人
大学と監査~その6 大学再編とガバナンス~ - 2018.11.29お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その6 大学再編とガバナンス~ - 2018.11.17お知らせ 公益法人
「公益information」のシステム更新の延期について - 2018.11.12お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて② - 2018.11.01お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて① - 2018.10.19お知らせ 公益法人
「公益information」のシステム更新について - 2018.10.09お知らせ 学校法人
大学と監査~その5 大学と業務監査~ - 2018.10.09お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その5 大学と業務監査~ - 2018.09.30お知らせ 行政・自治体
地方公共団体における内部統制制度に係る検討状況について - 2018.09.17お知らせ 行政・自治体
地方公会計の活用の促進に関する実務上の対応について - 2018.09.08お知らせ 行政・自治体
統一的な基準による財務書類の整備状況について - 2018.08.27お知らせ 学校法人
大学と監査~その4 私立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.27お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その4 私立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.13お知らせ 学校法人
大学と監査~その3 国立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.13お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その3 国立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.03お知らせ 学校法人
大学と監査~その2 私立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.08.03お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その2 私立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.20お知らせ 学校法人
大学と監査~その1 国立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.20お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その1 国立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.10お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準の改訂に向けての論点整理について - 2018.06.29お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体の包括外部監査制度の現状について」の公表について - 2018.06.18お知らせ 非営利法人全般
監査について⑥ - 2018.06.09お知らせ 非営利法人全般
監査について⑤ - 2018.05.26お知らせ 行政・自治体
「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」の公表 - 2018.05.12お知らせ 非営利法人全般
医療法人会計基準の概要 - 2018.05.01お知らせ 非営利法人全般
医療法の改正 - 2018.04.22お知らせ 非営利法人全般
みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について - 2018.03.16お知らせ 行政・自治体
統一的な基準に基づく財務書類の作成について - 2018.03.09お知らせ 非営利法人全般
監査について④ - 2018.03.02お知らせ 非営利法人全般
監査について③ - 2018.02.11お知らせ 非営利法人全般
監査について② - 2018.02.03お知らせ 非営利法人全般
監査について① - 2018.01.27お知らせ 行政・自治体
自治法改正④ - 2018.01.20お知らせ 公益法人
一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について - 2018.01.13お知らせ 行政・自治体
総務省自治体関連研究会の開催について - 2018.01.06お知らせ 学校法人
大学の会計について - 2017.12.28お知らせ 公益法人
「公益法人の会計に関する研究会」について - 2017.12.23お知らせ 独立行政法人等
地方独立行政法人会計基準等の改訂について - 2017.12.16お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体監査実務者研修会」の開催について - 2017.12.02お知らせ 学校法人
第4号基本金の計上に係る経過措置について - 2017.11.26お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準に係る論点の整理2 - 2017.11.18お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準に係る論点の整理 - 2017.11.04お知らせ 行政・自治体
地方自治体の会計基準とQ&A、注記例 - 2017.10.29お知らせ 行政・自治体
自治法改正③ - 2017.10.21お知らせ 行政・自治体
自治法改正② - 2017.10.14お知らせ 行政・自治体
自治法改正① - 2017.10.06お知らせ 公益法人
指定正味財産の考え方 - 2017.09.30お知らせ 学校法人
私立大学における23区の定員抑制 - 2017.03.16お知らせ 公益法人
「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について
- 2024.03.01お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会 報告書の公表について(その2) - 2024.02.16お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会 報告書の公表について(その1) - 2023.12.20お知らせ 公益法人
公益認定法施行規則改正に関するパブリックコメント結果について - 2023.09.05お知らせ 公益法人
令和5年度公益法人の会計に関する研究会の開催について - 2023.08.07お知らせ 学校法人
学校法人会計基準の在り方に関する検討会(令和5年度)の開催について - 2023.06.21お知らせ 公益法人
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告の公表について - 2023.05.01お知らせ 公益法人
「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告(案)の公表について - 2023.03.16お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その4)-私学法改正案の閣議決定・国会提出- - 2023.03.06お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その3)-監事、会計監査人- - 2023.02.20お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その2)-理事、評議員- - 2023.02.13お知らせ 学校法人
私立学校法改正の動きについて(その1) - 2023.01.26お知らせ 公益法人
特定費用準備資金が財務三基準に及ぼす影響について - 2023.01.05お知らせ 公益法人
公益法人の立入検査前のチェック項目について(その2) - 2022.10.20お知らせ 公益法人
公益法人の立入検査前のチェック項目について(その1) - 2022.09.15お知らせ 行政・自治体
総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」の開催について - 2022.08.24お知らせ 公益法人
大阪府所管公益法人における別表Hの対応について - 2022.07.15お知らせ 公益法人
内閣府「特費のすすめ」の公表について - 2022.06.29お知らせ 行政・自治体
地方公共団体におけるインボイス制度への対応について - 2022.06.08お知らせ 公益法人
「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」の追加等について - 2022.05.25お知らせ 非営利法人全般
非営利組織のモデル会計基準における純資産の区分について - 2022.05.10お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その4 - 2022.04.15お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その3 - 2022.04.07お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その2 - 2022.03.25お知らせ 学校法人
学校法人のガバナンス その1 - 2022.03.08お知らせ 公益法人
公益法人の定期提出書類等の様式変更について - 2022.02.09お知らせ 公益法人
内閣府「令和3年度公益法人の会計に関する研究会」(第51回・第52回)の議事公表について - 2022.01.19お知らせ 公益法人
「今なら間に合う!剰余金の解消策~特定費用準備資金~」(大阪府法務課)について - 2022.01.07お知らせ 公益法人
公益法人等に対する消費税課税について② - 2021.12.09お知らせ 公益法人
公益法人等に対する消費税課税について① - 2021.10.19お知らせ 公益法人
公益法人等に対する法人税課税について - 2021.09.13お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体包括外部監査に関する監査手続事例~公営企業編~」の公表について - 2021.09.02お知らせ 公益法人
公益法人定期提出書類「別表H」の改訂について - 2021.07.06お知らせ 公益法人
「決議の省略」における議事録・同意書の備置きについて - 2021.06.21お知らせ 行政・自治体
地方公営企業における消費税の決算上の取扱いについて - 2021.05.31お知らせ 公益法人
公益法人FAQの追加・修正について - 2021.05.10お知らせ 公益法人
「令和2年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」の公表について - 2021.04.16お知らせ 行政・自治体
監査専門委員の活用について - 2021.04.01お知らせ 公益法人
公益法人における「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」について - 2021.02.24お知らせ 公益法人
公益法人等の消費税申告における持続化給付金の取扱いについて - 2021.02.05お知らせ 公益法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正について - 2021.01.12お知らせ 学校法人
高等学校等就学支援金制度及び高等教育の修学支援新制度の会計処理について - 2020.12.28お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染拡大に係る家賃支援給付金の公益法人等への適用について - 2020.12.09お知らせ 公益法人
「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ案)」について - 2020.11.24お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その4)】監査委員と内部統制 - 2020.11.12お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その3)】 自治体における内部統制の特徴 ② 自治体における「内部統制の構成要素」の特徴 - 2020.10.30お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その3)】 自治体における内部統制の特徴 ① 「業務の効率的かつ効果的な執行」を重視 - 2020.10.14お知らせ 公益法人
公益法人等における持続化給付金の申請について - 2020.10.01お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2)】内部統制とは ③COSOの内部統制フレームワーク - 2020.09.23お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2)】内部統制とは ②日本にやって来た内部統制 - 2020.09.09お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その2】内部統制とは ①アメリカ起源の内部統制 - 2020.08.26お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(その1)】地方自治法の改正と内部統制について - 2020.08.13お知らせ 行政・自治体
【自治体内部統制シリーズ(序)】自治体内部統制シリーズ連載開始にあたって - 2020.08.03お知らせ 行政・自治体
統一的な基準による財務書類の作成状況等に関する調査について - 2020.07.20お知らせ 公益法人
大阪府における公益法人立入検査の実施について - 2020.06.29お知らせ 公益法人
「令和元年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」及び「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正」の公表について - 2020.06.11お知らせ 行政・自治体
「地方公会計の推進に関する研究会(令和元年度)報告書」の公表について - 2020.04.27お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(4) - 2020.04.14お知らせ 公益法人
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.14お知らせ 学校法人
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.14お知らせ 非営利法人全般
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた決算対応について - 2020.04.10お知らせ 学校法人
非営利組織の監査報告書の改正について(3) - 2020.04.10お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(3) - 2020.03.30お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の監査報告書の改正について(2) - 2020.03.13お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催についてその3 - 2020.03.12お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催についてその2 - 2020.03.02お知らせ 公益法人
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について - 2020.02.28お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会近畿会公開シンポジウム 「地方自治体の新たな時代の幕開け~内部統制制度制度導入への取組み~」参加報告 - 2020.01.20お知らせ 公益法人
第1回公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 - 2020.01.04お知らせ 公益法人
公益法人及び学校法人のガバナンス改革について - 2020.01.04お知らせ 学校法人
公益法人及び学校法人のガバナンス改革について - 2019.12.23お知らせ 非営利法人全般
日本公認会計士協会「非営利組織における財務報告の検討」について - 2019.12.03お知らせ 非営利法人全般
非営利組織の「監査報告書」の改正について - 2019.10.23お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準の改訂について(リマインド) - 2019.10.07お知らせ 学校法人
私立学校法の改正について② - 2019.09.25お知らせ 学校法人
私立学校法の改正について① - 2019.09.13お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公会計の論点と方向性」の公表について - 2019.08.30お知らせ 行政・自治体
総務省「地方公会計の推進に関する研究会(令和元年度)」の開催について - 2019.08.20お知らせ 公益法人
公益法人に対する勧告案件について - 2019.08.09お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について③ - 2019.07.31お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について② - 2019.07.16お知らせ 行政・自治体
日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について① - 2019.07.05お知らせ 行政・自治体
水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について - 2019.06.20お知らせ 行政・自治体
内部統制ガイドライン及び監査基準(案)の公表について - 2019.06.11お知らせ 公益法人
(公益法人)電子申請システムにおけるエラーコードについて - 2019.05.30お知らせ 公益法人
「公益法人information」新たな電子申請システムの稼働について - 2019.04.19お知らせ 公益法人
「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」について - 2019.04.08お知らせ 公益法人
「平成30年度公益法人の会計に関する諸課題の検討の整理について」の公表 - 2019.03.30お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について④ - 2019.03.22お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について③ - 2019.03.08お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について② - 2019.02.18お知らせ 学校法人
学校法人制度の改善方策について① - 2019.02.06お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて⑤ - 2019.01.07お知らせ 行政・自治体
総務省「経営戦略策定支援等に関する調査研究会」の開催について - 2018.12.28お知らせ 独立行政法人等
国立大学法人会計基準の改訂について - 2018.12.22お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて④ - 2018.12.10お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて③ - 2018.11.29お知らせ 学校法人
大学と監査~その6 大学再編とガバナンス~ - 2018.11.29お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その6 大学再編とガバナンス~ - 2018.11.17お知らせ 公益法人
「公益information」のシステム更新の延期について - 2018.11.12お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて② - 2018.11.01お知らせ 行政・自治体
都市の人口の動きについて① - 2018.10.19お知らせ 公益法人
「公益information」のシステム更新について - 2018.10.09お知らせ 学校法人
大学と監査~その5 大学と業務監査~ - 2018.10.09お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その5 大学と業務監査~ - 2018.09.30お知らせ 行政・自治体
地方公共団体における内部統制制度に係る検討状況について - 2018.09.17お知らせ 行政・自治体
地方公会計の活用の促進に関する実務上の対応について - 2018.09.08お知らせ 行政・自治体
統一的な基準による財務書類の整備状況について - 2018.08.27お知らせ 学校法人
大学と監査~その4 私立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.27お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その4 私立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.13お知らせ 学校法人
大学と監査~その3 国立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.13お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その3 国立大学における監査機能の強化について~ - 2018.08.03お知らせ 学校法人
大学と監査~その2 私立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.08.03お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その2 私立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.20お知らせ 学校法人
大学と監査~その1 国立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.20お知らせ 独立行政法人等
大学と監査~その1 国立大学の監査とその根拠法令~ - 2018.07.10お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準の改訂に向けての論点整理について - 2018.06.29お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体の包括外部監査制度の現状について」の公表について - 2018.06.18お知らせ 非営利法人全般
監査について⑥ - 2018.06.09お知らせ 非営利法人全般
監査について⑤ - 2018.05.26お知らせ 行政・自治体
「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」の公表 - 2018.05.12お知らせ 非営利法人全般
医療法人会計基準の概要 - 2018.05.01お知らせ 非営利法人全般
医療法の改正 - 2018.04.22お知らせ 非営利法人全般
みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について - 2018.03.16お知らせ 行政・自治体
統一的な基準に基づく財務書類の作成について - 2018.03.09お知らせ 非営利法人全般
監査について④ - 2018.03.02お知らせ 非営利法人全般
監査について③ - 2018.02.11お知らせ 非営利法人全般
監査について② - 2018.02.03お知らせ 非営利法人全般
監査について① - 2018.01.27お知らせ 行政・自治体
自治法改正④ - 2018.01.20お知らせ 公益法人
一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係について - 2018.01.13お知らせ 行政・自治体
総務省自治体関連研究会の開催について - 2018.01.06お知らせ 学校法人
大学の会計について - 2017.12.28お知らせ 公益法人
「公益法人の会計に関する研究会」について - 2017.12.23お知らせ 独立行政法人等
地方独立行政法人会計基準等の改訂について - 2017.12.16お知らせ 行政・自治体
「地方公共団体監査実務者研修会」の開催について - 2017.12.02お知らせ 学校法人
第4号基本金の計上に係る経過措置について - 2017.11.26お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準に係る論点の整理2 - 2017.11.18お知らせ 独立行政法人等
独立行政法人会計基準に係る論点の整理 - 2017.11.04お知らせ 行政・自治体
地方自治体の会計基準とQ&A、注記例 - 2017.10.29お知らせ 行政・自治体
自治法改正③ - 2017.10.21お知らせ 行政・自治体
自治法改正② - 2017.10.14お知らせ 行政・自治体
自治法改正① - 2017.10.06お知らせ 公益法人
指定正味財産の考え方 - 2017.09.30お知らせ 学校法人
私立大学における23区の定員抑制 - 2017.03.16お知らせ 公益法人
「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について
PICK UP NEWS一覧へ
-
2024.03.01お知らせ 学校法人
-
2024.02.16お知らせ 学校法人
-
2023.12.20お知らせ 公益法人
-
2023.09.05お知らせ 公益法人
-
2023.08.07お知らせ 学校法人

 大阪事務所
大阪事務所